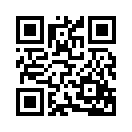今日は七草粥
2010年01月07日
 今日は1月7日。「七草粥」をいただく日ですね。
今日は1月7日。「七草粥」をいただく日ですね。お正月のご馳走続きでちょっと疲れ気味の胃腸を、ここで休めてあげましょう。
というわけで、美肌ママ家でも、今日は七草粥でした♪
春の七草と言われるのものは、芹(せり)、薺(なずな)、御形(ごぎょう)、繁縷(はこべら)、仏の座(ほとけのざ)、菘(すずな)、蘿蔔(すずしろ)です。
この“春の七草”を入れたお粥を食べる週間は、「七草の節句」とも言われているそうです。
日本のお正月の伝統行事ですね。
もともと七草粥は、平安時代の頃に中国から伝わってきたんだそうです。
古代の中国で七種類の野菜のお吸い物を食べて無病息災を願う風習があったみたいで、この風習が日本でも根付いたんですね。
今日は中華風の味付けにして、子供たちが食べやすいように卵を入れてみました♪
卵を入れると、七草のアクや苦味がだいぶ和らぎます。
でも、この子供たちには気になる七草野草のアクや苦味に、季節に応じてカラダが求める有効成分が入っているんだそうです。
七草にも、アンチエイジングにいい成分がたっぷりですよ!
[せり]
増血作用・・・鉄分が多く含まれています。
[なずな]
解熱、利尿作用があります。
[はこべら]
タンパクが多く含まれています。またミネラルやそのほかの栄養に富んでいます。
むかしは薬草として使われていました。
[すずな・すずしろ]
消化促進作用があります。
いろんな作用や栄養があるんですね~。
年に1回しか食べませんが、昔の人は体にいいものをちゃんと知っていたのですね。
古くからの風習にはちゃんとした意味があるんだなと思いました。